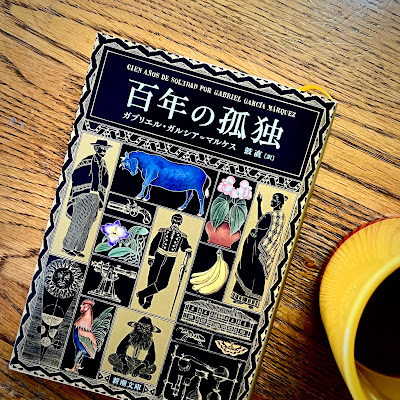古いカセットデッキを持っている。
TEACのR-606Xという機種で、今はもう動かないがいずれ修理して大量にある過去のカセットテープをまた聞き直そうと考えていた。そう考えてから随分年月が過ぎた。
でも昨日たまたまBluetooth対応のコンパクトカセットプレーヤーなら車内で再生して聞くことが出来ると知ったので早速MaxellのMXCP-P100という製品を注文したら今日それが届いた。納戸の奥からテープを出してきた。100本ほどもあったがもう聞かないのを捨てたら50本が残った。
最初クルマで再生してみたらうまくいかなかったのでiPhoneとの接続を切ってやってみたらうまくいった。その後再びiPhoneと接続して切り替えできるようにした。部屋でも聞けるようにカセットプレーヤーのイヤホンジャックでlogicoolのZ120というコンパクトスピーカーに繋いだ。
面白くなってどんどん聴く。
整理したカセットを見ると松田聖子が5~6本もあって驚いた。こんなに聞いていたのだ。中学2年のときに友人のOから譲ってもらった中古のカセットプレーヤーを使ってラジオから録音したビートルズや谷村新司の曲の入ったテープなど、ほかにも懐かしくて胸が詰まる思いのするテープが何本もあった。
もう亡くなったTが大学時代に恋人の兄からプレゼントされたオフコースのテープのコピーや、大学浪人時代の19歳の初夏から秋にかけて録音したこずえの深夜営業のテープなど、とりわけハイファイセットのファッショナブルラバーを馬場こずえさんが紹介しているテープがなかなか見つからなくて苦労したがJimi Hendrixとだけ書いたソニーの120分テープに入っていた。谷山浩子のオールナイトニッポンのテープも懐かしい。
破損したテープもいくつかあってこれもなんとか修復した。
壊れたカセットデッキと大量のカセットテープをどうするか、保留のまま過ぎた年月はあながち無駄ではなかったのかもしれない。
12月25日
50年前、僕が高校生の時にラジオから録音したMJQのテープをカセットプレーヤーで聞く。これを録音した16歳頃の自分。50年後の自分がたった今それを聞いていると知ったらどんな顔をするだろう。50年経ってもまだそんなことをやっているのかと呆れるかな。
聴いていると、それはまさに雑音だらけの音の中からあの頃の胸苦しさが生々しく蘇ってくる。それと、これは折にふれて思い出す霧深い街を彷徨う小説のこと。ヌーヴォー・ロマンで検索したらミシェル・ビュトールの時間割という小説だった。出版が1975年だから僕は18歳か19歳の浪人時代。もう一度読みたくなってメルカリで注文した。
2025/12/26